師走が忙しい本当の理由
師走は忙しいは本当か?場合によっては疑わしく思っている人がいることも事実です。
それは単にその人やその職業が忙しくないというわけでもないようです。
むしろ普段から忙しく師走になって急に仕事が忙しくなったと感じてるわけではないというケースもあります。

このようなことからも師走だからといって本当に忙しいのか疑問に思う人も多いようです。
ですが本当に忙しいと思っている人も多く、その言葉は嘘ではないとも言えます。
ただし実際にその理由を見ていくと多忙なのは仕事によるものもばかりではないようです。

プライベートに関することなどもその理由で人によって様々ですね。
例えば、プライベートの場合は慌ただしい理由にクリスマスや年末年始の準備を挙げる人もいます。
これに加えて年賀状の準備などが入ってくるためプライベートの部分で忙しくなる人が出てきます。

また年末年始になれば殆どの職業で仕事納めということになるためです。
それで仕事をこなさないといけないということが多用となる理由としてあげられています。
田舎に帰省すれば、仕事をセーブせざるを得ないため、それまでに仕事を片付けることも求められます。
このように、やることが年末にかけ増えることでせわしないのも事実です。

それによって自ずと作業量が増えるため多忙となると考えられます。
フリーランスや個人事業主となると年末までの収支を報告しなければいけないです。
そのために節税対策などの業務は、年内にしておく必要がありますね。
このような頭を悩ませるケースのほかにも企業の経理担当などは、年末調整の準備もしないといけません。
社員やアルバイトなどの年末調整、そしてボーナスに伴う給与計算などやるべきことが増えることなども考えられます。

また、年が変われば方針も変わる企業も多いためこの年末の期間が仕事も忙しくなってきます。
それに合わせて最後の総仕上げにかかる人が多いことも師走が現代でも通じる言葉の1つとなるわけです。
これとは別に忘年会と称して飲み会が増えることも忙しいと感じることにつながります。
予定らしい予定がこれまでにあまりない中で12月に入って急に仕事や集まりなどの予定が埋まりだします。

こうなると心理的に忙しいと感じるようになるものですね。
このように年末にかけて仕事を片付けていくことや予定が詰まっていることが大きく影響しています。
単に仕事だけではなく複合的な要素が手一杯とさせてる可能性もけっこう高いです。
つまり結論からいえば師走は忙しいは、嘘ではなく本当ということです。
専業主婦でも師走は忙しいと感じる人は多くいます。

家事だけでなく大掃除など別のこともしなくてはならないことで多用となり忙しく感じることもあるからです。
これは予定が立て込む分、濃厚な1日を過ごすことになり、気が抜けない日となるからです。
ただサラリーマンなどの会社員からフリーランスや個人事業主、主婦とそれぞれ師走の忙しさの感じ方は違いますね。
師走に忙しい職業
師走になると忙しくなる職業や仕事は、何かも気になるところですね。
まず忘年会が行われ出すことから飲食業はこの時期が稼ぎ時になります。
この時期になるととても慌ただしく人手が足りなくなり急いで人員募集を始めることもあるほどです。

このように12月中旬から年末にかけ一気に忙しくなるのが飲食業です。
アルバイトの学生もまだこの時期は学校があるので時間に追われています。
学校で授業をこなしながら夜は夜でアルバイトという生活をしていると非常に忙しいと感じることは言えます。
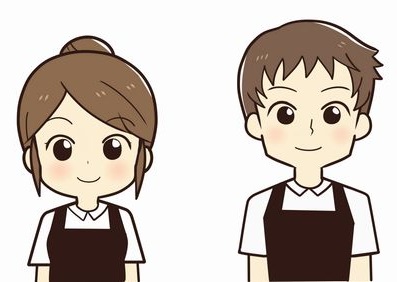
このように年末が商売のチャンスとなる職業はかなり忙しく感じるはずです。
年末が勝負という点では小売業なども非常に忙しい日々を過ごします。
お歳暮やクリスマス商戦、その先のお正月に向けた準備をしていくことになり休む暇がないのが実情です。
クリスマスやクリスマスイブについては、師走のこの時期の一大イベントです。

なお、忘年会やクリスマスに関連した記事を下記のページに詳しく紹介しています。
こちらも是非参考にしてみてくださいね。
あわせて読みたい記事
・残業好きの人たちの理由に驚愕!手当つかなくても?嫌いな人の意見も!
・お歳暮のバイトはきつい?仕事の種類や内容と時給はいくらで募集時期はいつの体験談!
・忘年会の意味!その由来や行なう目的と時期、いつから始まったのか?
最近では、お正月に店を開けるところとそうでないところがはっきり分かれています。
お正月に店を開けるということは、それまでにある程度準備を済ませなければならないということにもなり時間に追われます。
福袋をお正月に売り出すところは、元日に向け年末ギリギリまで作業をするところも多いです。

福袋に商品を詰める作業を一つ一つ行うため、これはかなりの重労働となる仕事です。
また、特定の職種で考えると事務作業、デスクワークを行う人も相当忙しくなります。
年末までに片づけるべきものが多く、その処理を済ませなければならないため多用となります。
経理であれば、年末調整のことや他にも各種手続きを済ませることも求められます。

経理などは、どの時期もある程度忙しいのではという意見もありますね。
しかし間違いが許されないという点では、師走の方が神経を使いやすいという実情もあります。
その作業量が多くなればなるほど、それなりにやるべきことは増えていくということです。
他にも師走に忙しい定番の職業が営業職でこの時期になればかなり忙しくなります。

年末商戦に絡んでいるところなどは、ここで一気に稼がないと大変なことになるからです。
決算は年度末でもボーナスが出る12月が大勝負になります。
そのため、それ以降にはあまりそうした場面にはなりません。
少しでも稼ぐためノルマもきつくなりそれをこなすためにあわただしくかけまわる営業マンも増えます。
セールスを行う人たちも同様であり、お金が一気に動くこの時期は忙しさが増してきます。

それを少しでもつかまえようとする人たちの動きも益々(ますます)激しくなります。
このように見ていくと師走に忙しい職業は実に多く仕事だけで相当大変なことがわかります。
これにプライベートが加われば、ゆっくり家で寝られることがいかに贅沢であるかを理解できます。
年末年始クリスマスなどに向けて日本全体が1つの方向に目がけて走りだすような形ですね。
師走に忙しくない職業
郵便局や小売業などはこの時期になれば忙しいです。
しかし、一方で師走になっても忙しくない職業や仕事があります。
例えば、自動車教習所は12月の時期は普段通りというより日程的にもとても楽な状態で暇となります。

メインとなるのは学生であり学生は休みの時期に集中し免許を取り始めます。
18歳になった高校生もこの時期は、まだ学校に通い免許取得の許可が出ていないところも少なくないです。
そうなると12月は、かえって暇な閑散期(かんさき)となるところが多いです。
意外なところでは、会計税務の仕事は師走でも普段と変わらない、むしろ静かな状況になります。

基本的に確定申告の時期や法人の決算時期に繁忙期を迎え2月や3月、半期決算の9月に集中します。
このような理由で会計税務の仕事は、そこまで多忙にはならないということです。
本来、12月になった瞬間、どこの職業でも一気に忙しくなるものです。
しかし会計税務のように別にピークが設定されているところでは忙しくならないということです。
職種で見ていくと研究開発の部門は普段と変わらない日々を過ごすことになります。

では、なぜ師走に忙しくなる職業があるかといえば、まず物を売る業種がその代表ですね。
一気に大量消費が行われ、それを供給していかなければならないために忙しくなるわけです。
研究開発などは、これらに全く関係がないので年中マイペースのところが多いです。
忙しいと感じることはプライベートのことぐらいで師走になって急に仕事に追われだすということはないです。

あるとすれば、年末年始にしっかりと休むからということですがそれもかなり限定的です。
年が変われば気分もガラッと変わるのは誰でも皆、同じことですね。
明日できることは、今日やるべきだというのはわかっていてもできないものです。
習い事や人材派遣、転職系関連の職業は、お正月以降に一気に動き出すこともあります。

しかし、この時期はあまり活発にならないのもこの業種の実情です。
習い事の場合は、この時期に始めてもまとまった休みを挟むため敬遠するというのもあります。
転職系などは来年から本気を出すという人も多く年末年始になればなるほど動かなくなる業種です。

多くの人が多忙になるということは余暇に時間を割けないことでもあります。
そうしたサービスを展開する業種ではまず忙しくなることはありません。
師走の忙しさが一段落した時期に逆に一気に忙しくなりそれでもそのような業種は少数派と言えます。
師走で忙しい時期はいつからいつまで
師走で忙しくなるとはいえ、いつからいつまでが忙しい時期になるのかを分かっていない部分があります。
師走に入る12月1日から急に多忙になるケースはあまりないです。
すでに、その前からずっと忙しいと感じる人も少なくありません。

今は、師走に向けて本当に多忙になるのは実は11月の終わりごろからなんです。
12月に入ったことでこれらの状況が加わってさらにそう感じるようになるというのが真実と言えます。
また、冬のボーナスが支給されるタイミングを前後して忙しくなるという考え方もできます。

公務員などは12月10日にボーナスが支給されることから、これに向けて勝負をかける小売業が多いです。
11月の終わりごろから勝負をかけるところや12月1日になって広告を打ち始めるところもあります。
また、支給日の前後に営業をかけるところなどタイミングは様々です。
勝負をかけるということはそれだけ忙しくなることを意味していますね。
民間企業は支給日にバラつきがあるため公務員のボーナス支給日を中心に考えていく方が計算がしやすいです。

そのため師走で忙しさのピークを迎えるのは12月の中旬ということになります。
12月の前半はいわゆるボーナス商戦であわただしいです。
では12月の後半はどうでしょうか?
こちらは間違いなく、お正月に向けて大忙しといったところです。
この時期になると年賀状の準備などに追われる人が多くなります。
そのためにパソコンやプリンターと年賀ハガキ、インクなどを準備して休みの日に印刷をして出してしまう人も増えます。

郵便局も年賀ハガキを売るためにと郵便局を飛び出して駅などで売る姿も見られます。
そしてハガキが投函されれば、今度はそれを仕分けしてお正月に配達します。
当然のことながら郵便局は、正にこの時期は忙しいといえます。
実際に師走が忙しいと感じる年代は50代60代が多く若い世代はあまり感じていないのが実情です。
50代60代の性別でいうと特に女性が忙しいと感じることが分かっています。

その理由として、おせち料理大掃除、あとは年賀状の準備などやることが多いのが挙げられます。
これにスーパーマーケットのパートなどが加われば暇がない感じることが普通です。
こう考えたほうがよく、なぜ大変なのかという理由が職業、年齢、性別などで違うということです。
若い世代は、おせち料理に力を入れることは少なくなりました。
しかし50代以上は、まだその文化があるので年末年始は非常に大変な日々を過ごすということです。

なお、師走のこの時期にある行事にすす払い(煤払い)があります。
この行事も50代60代にはなじみ深い行事で知られています。
煤払いや掃除をすることで、お正月に年神様をお迎えするための新年の準備のため行なわれます。
そこでもうひとつ師走(12月)の有名な行事に針供養というものもあります。
これらの行事についての詳しい記事を下記のページに紹介していますので参考にしてくださいね。
あわせて読みたい記事
・元日と元旦の違い?正確な日にちや時間と使い分けの仕方の例と意味!
・針供養の2018年と2019年はいつ!日にちや時間と場所はどこ?
・すす払いの意味!行なう理由や由来と掃除との違いや事始めとの関係?
・おせち料理はいつ食べるものなのか?地域による違いや食材の意味も紹介!
・おせちの重箱の意味と三段と五段の違い?食材の詰め方も紹介!
・おせちの海老(えび)の意味!おすすめの種類とエビチリを入れるのはおかしい?
12月の前半はボーナス絡みの忙しさ12月後半は、お正月に向けた忙しさがあるので中身が異なるような状況です。
いつからいつまでというよりは師走は、どの時期もせわしないということですね。
このように師走に入ると仕事や家事だけではなく神社やお寺での行事も増えてくるなど多忙となってきます。
師走の由来や語源
旧暦の12月のことを師走といいますが新暦の今も12月の他の呼び方という意味で多くの人に把握されていますね。
この師走の由来や語源についてです。
ですが、師走という言葉は当て字であることが明らかになっています。

漢字だけを見れば師が走ると書いているので師とされる人が走るほど忙しいという意味に見えます。
しかし実際は、「お坊さんがお経を読むために家々から招かれていた」ことから始まっています。
この説は、平安時代に出てきたもので古くからあります。
この時点ですでに語源がどこから来ているのかわからない状態だったと言われその真偽は定かではありません。
ですが語源や由来に関してはいくつかの説があり、そのどれも有力な印象を与えます。
師走は四季の果てる月なので、四季を極めると書いて四極、シハツと呼びそれから転じた説もあります。

何かが果てる月だったという説は、ほかにもあり年が果てる月などがあり、これらも決め手に欠ける状況です。
平安時代、鎌倉時代までは、師馳せ(しはせ)、江戸時代には師走になっています。
この間に何かしらの変化があったことは間違いないですが当て字であることは確実です。
師が走るから付けられたという説も国語学者からはあまり支持をされていないようです。
師走の実際の由来は定かではなく10以上の説があることからもベールに包まれていることがわかります。
現代は師を先生と捉え医者が走っていたのではないかという説を唱える人もいます。

しかしこれは、明らかに違います。なぜなら「しわす」という言葉は、奈良時代からあったためです。
当初は十二月と書かれていて12月をそのように言う言葉はすでに存在していました。
それが江戸時代あたりで当て字でそうなったということに過ぎません。
1月から12月につけられた旧暦の多くは、実は当て字だったという事実はあまり知られていません。

例えば神無月は神の無い月、これを水無月は水のない月と教わった人も多いはずです。
ですが、実際は無という意味は無いという意味ではなく連体助詞です。
このことから神の月や水の月という意味合いであることが指摘されています。
漢字だけで考えると大きな間違いをする可能性が高いようです。
今回のケースでも漢字だけで判断をすることは避けた方が良さそうです。
旧暦など昔からの言葉は不明な点が多く語源や由来に関してもいくつも説があるのが普通です。
しかし、丁寧に振り返ってみると実はちゃんとした意味があったり有力な説があったりするものです。
これをきっかけに他の旧暦に関して調べてみるというのも面白いですね。
師走が忙しい理由|まとめ
師走は忙しい本当の理由についての記事はいかがでしたでしょうか?
本当に師走が忙しいのかそれとも忙しくないのかは職業にもよります。
そこには現代社会の仕組み上、普段から慌ただしい状態が毎日続いていることも挙げられます。
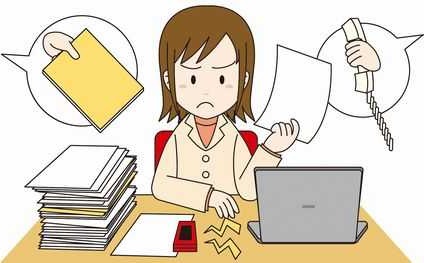
そのため、師走になってから急に忙しくなったと感じないという意見も見られましたね。
また、忙しくなる理由についても仕事上のことだけではないようです。
仕事以外にも忘年会もあり、年賀状の準備もあり多忙となります。
主婦には、大掃除やおせちの仕込みなどの忙しさもありましたね。
![]()

なお、師走は忙しくないという暇な職業も確実に存在していました。
それにも理由があり、年末だからといって特別仕事内容が変わらないということです。
中には、自動車教習所のように世の中忙しい時期だからこそ暇な職業もありましたね。
この時期は忙しくなる人が増えるので免許を取りにくる時間の余裕もなく、かえってここが暇になるというのが本当の理由となるようです。
もしこのような師走に関係ない職業についている方などでしたら大晦日もゆっくり楽しむことが可能かもしれませんね。
大晦日の過ごし方については、下記のページに詳しく紹介してみたので参考にしてください。
師走も忙しくなる時期も変わりつつあり今の時代、12月からというより、むしろ11月の終わりごろからです。
いつまでかということなら、ここは間違いなく殆どの職業が年末ぎりぎりまであわただしいということです。
ここまでの例を見ると、どの職業にも言えることですが、忙しさとそれに見合う賃金にはまだまだ開きがあるようですね。
今年も師走を迎えるにあたり今日のこの記事がお役に立てると嬉しいです。



コメント