立志式の作文の書き方
立志式の作文の書き方ですが、ポイントは名文を書こうとしないことです。
そして、繁文縟礼(はんぶんじょくれい)にこだわり過ぎないことです。
この繁文縟礼とは、簡単に言うと決まり事や礼儀のことです。

立志式は、普通の儀式のように単に祝意を与える受けると言った受動的な立場で参加するわけではないです。
そのためこのセレモニーにあっては、作文を事前に準備することの重要性が非常に高いわけです。
ですが普段から文章を書く習慣のない人にとっては立志式の作文の書き方自体がよくわからないというのが現状ではないでしょうか。
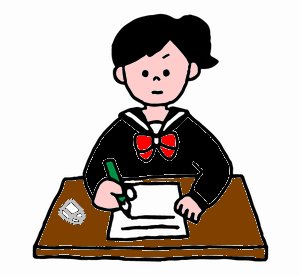
そこで、ここでは具体的な作文の書き方の原稿を紹介します。
作文を書くときに親御さんでも子供でも立場は違っても共通することがあります。
それは、普段心ひそかに抱いている感謝やねぎらいの思いを率直に文章にすることを心がけることです。
人目を気にするばかり、体裁などにこだわりすぎると素直に相手に伝えることができません。
いたずらにまわりくどい迂遠(うえん)な内容になってしまうことがよくあるからです。
立志式の作文を書く流れ
見本となる立志式の作文や手紙はこれまでの成長と、これから先成長していくことを書くことです。
そして、自分の将来像を確認するという流れで進めていきます。
文章の流れになると考えれば、間違いはないでしょう。
①これまでの中学生活に至るまでがんばってきたことを振り返り。
②高校などの直近の目標や将来の夢を紹介してから。
③その目標に到達するために何に取り組むのか野流れで文章構成を検討すれば自然な流れになりそうです。
しかし自分で書いた文章を読むといっても双方向のコミュニケーションを前提にしています。
具体的に何を書けばいいかわからない場合にこちらの本もおすすめです。
子供からの言葉に答える形で親御さんも作文を作詩(さくし)してそれを読んで思いを返すというスタイルになっています。
すなわち立志式に置いては親御さんも子供さんもそれぞれの立場でこのセレモニーに積極的に関与することになるのです。
立志式の作文を書くときの注意点
立志式での作文はこれから先、成長して大人になるためのものです。
立志式の作文で、決意表明の位置づけをすることが出来ます。
作文を披露して親に感謝の気持ちや将来の目標や理想を発表します。

こうして人間像などを明らかにすることが流れの軸になっています。
同時にこれまでの自分を形作って今日に渡る軌跡を改めて振り返るという側面も持っています。
注意点はパクリではなく、あくまで例文を元に自分の決意表明となるよう書くべきです。
どのように文章を書けばいいのか、とっかかりも見つからない。
このようなときは一つの見本として参照してみて下さい。
立志式の作文の例文
立志式での作文の見本となるの例文の原稿です。
おすすめなのは中学生になったときに決意したことです。
目標、これまでの思い出や感謝の気持ちをまとめてみるというのも良いでしょう。
【立志式での作文の見本となるの例文の原稿】
何となく周囲の雰囲気に流されがちだった性格の私でしたが、中学校にあがったときには決意したことがあります。
それは何かを一生懸命に取り組んで、人として成長するということです。
人間として成長できるためには勉強だけでなく部活動にも積極的に参加しました。
より多くの人たちとのつながりを持ち、新たな自分を発見できたらと入学当初から決心していたのです。
部活動には運動系と文科系がありますが、小さな頃から体力にあまり自信がなく運動も苦手です。
ですが、これまでの自分を変えたいとの一念からも運動部に入部することにしていました。
入学してからのしばらくの間は練習どころか準備運動するのも体力的にきつかった時期もあったのは事実です。
しかし同じ苦しみに向き合う仲間とちと励ましあいながら、何とかあきらめずに続けることが出来ました。
もちろん入部した以上はレギュラーポジションを狙って練習に打ち込んできましたが、なかなかサブの位置から抜け出すことは出来ませんでした。
レギュラーには結局なれそうにもありませんが、それでもなお厳しい練習に向きあった仲間達は、大事な友達になってくれています。
部活動だけでなく友人関係のことや勉強などで壁に直面しても話しに耳を傾けてくれる友人たちを作ることができたのは、貴重な財産になりました。
勉強面では苦手科目などもあるので、志望校に受かるためには一生懸命勉強しなければならないでしょう。
しかしこれまでの部活動での経験のおかげで多少きついことも乗り越えていけそうです。
そして家庭では私を支えてくれたお父さんやお母さんに心の底からありがとうございます。と感謝の言葉を送りたいです。
立志式の作文で親から子供への例文
親から子供へ作文や手紙を手渡すといった内容を盛り込んで行われることも多いです。
年齢に応じてとり行われる儀式には七五三や成人式などは誰にも馴染みがあるものです。
成人式を迎える子供や孫のために晴れ着を年長者が贈るというのは風物詩の一つになっています。

親御さんからすれば、子供が立派に育っていく姿を夢見ていることでしょう。
このセレモニーはキャリア教育の一環として学校現場で採用に至ったものなので登場して歴史が余りありません。

なかにはこういった儀式の経験がなかったりする方も少なくないです。
父や母の立場などから自分の息子や娘に対して作文や手紙を当てて書くというのも、お祝いに選考されがちです。
何を書けばいいのかよくわからないことも多いものです。

そこで立志式で手渡すことになる手紙などの見本となる書き方や例文も紹介します。
立志式での作文ではこれまで取り組んできたことや将来の夢などについて触れるものが多いです。
これまでの努力を見守ってきたことや、将来の目標達成のための不安を励ます言葉などを盛り込んで。
「これから、いつもがんばって来たあなたを誇りに思います。この先も応援するよ。」
このような文章で締めくくるのが全体の流れです。
中学生やその親御さんには立志式の作文の他にも、式での服装や卒業文集など今後もいろいろとあります。
それらも書きで記事にしてみました。
あわせて読みたい記事
・立志式の手紙を親から子供へ贈るときの書き方!例文と解も伝授
・立志式とは!目的と中学3年生がやるのはなぜ?由来も調べてみた!
・立志式で保護者におすすめの服装は?母親と父親や子供の場合もご紹介!
・中学校の卒業文集の書き方!将来の夢と修学旅行や部活の思い出の例文?
親から子供への見本となる例文
親から子供に贈る作文や手紙の例文は、下のような作文や手紙を子供に贈ると親の愛情が伝わりやすいです。
立志式の作文は例文を丸パクリするのはなく、これはあくまで見本です。
例文を参考に、あなたからお子さんに伝えたいオリジナルなことを書くことが大事です。
【親から子供への見本となる例文の原稿】
・中学三年生になってあなたは本当に成長したとお父さんもお母さんもあなたの成長振りに嬉しい驚きをもって、今日の日を迎えることが出来ました。
・中学校に入学したときに本が好きなあなたは文科系の部活を選ぶと持っていましたが、運動系のクラブを選ぶと聞いて正直私たちは不安になったものです。
・小さな頃はよく風邪を引いて熱が出たり喉をいためることがあなたは多かったのを覚えていますか。
・私たちは幼少の頃の病気に弱かったわが子が本当に部活動についていけるのか、心のそこから心配したものです。ところが蓋を開けてみると、私たちの心配は杞憂に過ぎなかったことがわかりました。
・はじめのころは練習に追いつくだけに必死だったのに、中学二年になるとレギュラーの座も可能性がでてきたのを聞いて、嬉しい驚きを感じたものです。部活動だけでなく、勉強の方にもあなたはがんばっている姿を見ていました。
・苦手な科目に向き合い、先生からは到底望めない言われていた志望校についても受験してみてもいいと指導を受けるほどになりました。
・あなたの成長振りには本当に嬉しく思っています。あなたのこれまでのがんばりを見ているので、これから先困難な自体があっても切り抜けて埋けるでしょう。」
このような作文や手紙を子供に贈ると親の愛情が伝わりやすいのではないでしょうか。
立志式の作文の書き方|まとめ
立志式(りっししき)の作文の書き方や例文っていざ書こうと思うと悩みますよね。
中学3年生を対象として行われている行事のことです。
人生についての設計を見定めることを目的とした作文を書いて発表します。

「学生のころ経験したことがある」という方もいるのではないでしょうか?
自分が親になってから「参加した」という方もおられると思います。
中には「自分が学生のときも親になってからのどちらも参加したことがない」という方もいます。
また「なにそれ?」って方もいるとおもいますので何のことをいうのかも説明していきます。

この立志式という行事は、このように地域や年齢などによって認知されている度合いも結構違います。
なお、学生からだけではなく親から子供へ手紙や作文を贈るところもあります。
立志式の作文の書き方の記事と見本となる例文や親から子供への場合はどうするのか?
子供からの言葉に答える形で親も作文を作詩(さくし)してそれを読んで思いを返すというスタイルです。
なので、どちらも立志式の作文の例文を丸パクリするのはおすすめできません。
例文はあくまで参考程度にして、自分の想いを書くようにしましょう。
親から子供への場合は、これまでの努力を見守ってきたことや、将来の目標達成のための不安を励ます言葉などを盛り込むのがおすすめです。
立志式の意味や由来ですが、立志式とは単純化して言えば、昔の成人式に相当する儀式になります。
内省(ないせい)の機会を与え力強く自ら積極的に人間として成長するためのセレモニーとして立志式が重視されています。
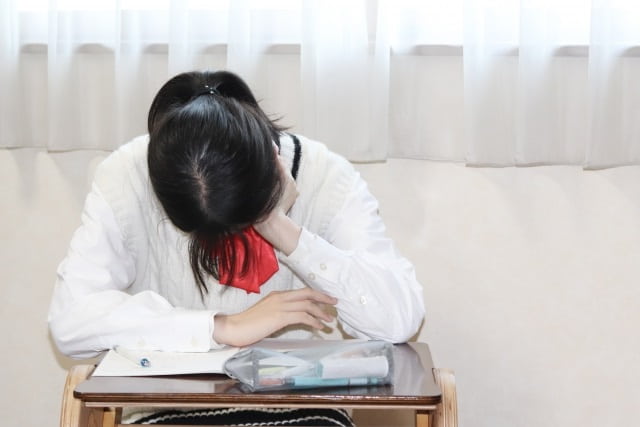












コメント
おおおおおおお
あ
わわわわ
おおおおおおーーーーー
参考になりました
こんにちは。参考になれば幸いです。
コメントありがとうございました。