バレンタインデーはいつから
バレンタインデーは、いつから始まった風習なのかは諸説あります。
3世紀のローマ帝国が起源とされる説が有力です。
2月14日はローマにおいて神々の女王であるユーノーの祝日でした。

バレンタインデーは聖バレンタインデーとも呼ばれ、毎年2月14日に世界各地で行われるカップル同士の愛の誓いの日となっています。
日本では主に女性が男性にチョコレートをプレゼントする事が、一般的に浸透しています。
その翌日の2月15日はルペルカリア祭りという豊作祈願の祭りが行われていました。
その時代の男女は別々に生活をさせられていました。
この祭りの期間だけは、くじ引きによって決められた相手と一緒に過ごす事が認められていたのです。

これによって多くの男女が結婚に至ったと言われています。
ローマ帝国の皇帝であるクラウディウス2世が、それを阻んでいました。
兵士達が愛する家族がいると、戦意が失われ士気が下がる事を懸念して結婚を禁じていました。
それを知った皇帝は許すはずもなく、バレンタインに対して二度と行わないように命令します。
バレンタインはこの命令を聞き入れずに同様の事を繰り返していたため、処刑されてしまいました。

処刑が行われた日は2月14日、ルペルカリア際の前日に処刑され、祭りに捧げる生贄とされたと言います。
恋人達に尽くし、若者の愛のために命を落としたバレンタインを称えて、この日は祭日になって恋人達の日としています。
これが、定着していったというのが起源として有力な説となっています。
これらの説には歴史的な側面などから見た考察が必要ですね。
キリスト教に関する視点からの解釈など細かい点から確認する事も大事でしょう。
バレンタインはその後世界中に普及していきカップルが手紙やプレゼントを渡したりする人なります。
日本では女性からの気持ちとしてチョコレートを贈るなど、色々な形で浸透していきました。

この形は各国で違いがあり、西ヨーロッパでは男女が共にギフトを贈り合う日となっています。
ベトナムなどでは男性が女性にサービスをして尽くす日など、国によっては近年まで行われていなかった国もあります。
知名度や習慣もそれぞれ多様となっています。
バレンタインデーを日本で流行らせたのは誰
日本ではバレンタインデーに女性から男性にチョコレートを贈るというスタイルで普及しています。
では、このイベントを流行らせたのは誰なのかという事はいくつかの説が存在します。

発展の経緯は日本独自の形で、流行し始めたのは1958年頃だとされています。
それ以前から普及させようという動きはありましたが、あまり定着せずにいたようです。
バレンタインデーを流行らせた第一人者が誰であるかという説をいくつか紹介していきます。
「洋菓子店モロゾフの提唱」1936年に神戸の洋菓子店のモロゾフ株式会社がそのひとつです。
外国人向けの英字新聞に「バレンタインにチョコレートを贈りましょう」という広告を出しています。

確認されている中では1番古い時期で、最有力となる説です。
メリーチョコレートがデパートで行ったセールも有力です。
1958年メリーチョコレートが、伊勢丹新宿本店で行ったバレンタインセールが商業的な部分での最初だともされています。
これが、現在の風習の走りとも言えるでしょう。
「森永製菓の新聞広告」1960年に菓子メーカーの森永製菓がバレンタインの新聞広告を大々的に掲載しました。
ブームの兆しを見せ始めていた業界を、さらに加速させるきっかけになった要因でもあります。
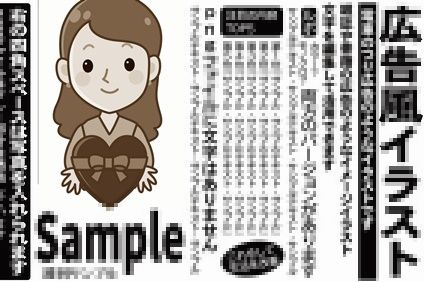
「ソニープラザの提唱」1968年にソニーの関連輸入雑貨店であるソニープラザが、バレンタインの販促企画をしたこともあります。
創業者の盛田昭夫(もりたあきお)氏が「バレンタインデーを日本で流行らせたのは我々」だと宣言しています。
以上の説がありますが、全くバレンタインデーが認知されていなかった時代での提案です。
当時の宣伝内容はまだ女性から男性に贈るという事に限っていませんでした。
愛の形として贈り物をしてそれにチョコレートを添えるといったスタイルが主流でもあったようです。

ちなみにバレンタインゆかりの地であるイタリアのテルニ市から、モロゾフ製菓がある神戸市に愛の像が贈られています。
これは日本におけるバレンタインデーの発祥の地としての証を記念して贈答された物です。
バレンタインデーにチョコレートを贈る意味
日本ではバレンタインデーにチョコを贈る事が定着しています。
この時期に年間の2割程を売り上げるとも言われています。
なお、バレンタインデーにチョコを贈るという習慣は日本独自の風習です。

世界の各国では違う物を贈りますのでこういった文化はありません。
日本がなぜチョコをプレゼントするようになったか?
有力な説として高級なお菓子であったチョコレートを普及させるという側面が見受けられます。
これに追随して各菓子メーカーも提案をしていきます。
外国の文化に習って「バレンタインデーには愛を伝えましょう、そしてチョコレートも添えて」手紙などを贈りましょう。
といったキャンペーンを展開していき、高級なお菓子は贈り物にも最適だというメリットをアピールしていきます。
これによって売り上げは増加して、菓子メーカーとしても販売しやすい商品となりました。

日本では2月14日は冬場で気温も高くありませんので、溶けたりしにくい部分もメリットと言えます。
その後徐々に価格も手頃な範囲になり、当初は夫婦の間でのやり取りを想定していたバレンタインでした。
それが、学生などの世代にも定着が進んでいきます。
学生たちは自分たちからバレンタインの文化に乗っかって行った部分もあります。
ブームとなるきっかけ作りに大きく貢献していると言えるでしょう。
学生たちの間では、贈るお菓子によって意味がそれぞれあるという設定を作ることもあります。
※チョコレートを贈る相手は本命
※クッキーであればお友達
※マシュマロなら相手の事を嫌っている
このように、学生特有のルールを作ったりもしているようです。

このような理由でバレンタインデーに贈られています。
ですが、男女のお菓子として適しているとされる説があります。
チョコレートには、フェネチルアミンという恋愛化学物質が含まれています。
しかしこの恋愛化学物質が男女のイベントにプレゼントされるお菓子に含まれているというのは、何かの意味を考えてしまいますね。
バレンタインデーの由来と起源
日本では、1958年頃から普及し始めたバレンタインデーが起源です。
その由来としてはどのような経緯をたどってきたのでしょうか。
各メーカーが展開していたバレンタインデーですが、当初は中々浸透していきませんでした。

愛を伝える日という軸はありました。
しかし、まだ誰が誰に贈るのかや何を贈るのかは限定されておらず曖昧な部分がありました。
そして徐々に女性から男性にチョコレートを贈るという部分が定着していきます。
主に最初は、夫婦を想定して展開していました。
未婚の恋人同士や女性から男性への告白にも利用されるようになります。
義理チョコの意味
1970年代に入ると特に恋愛感情の無い相手や、職場の男性に配る贈るいわゆる「義理チョコ」などの文化も登場します。
こちらは書いて字のごとく義理といったところでしょう。
チョコのプレゼントを貰う男性にとっては、嬉しいのか辛いのか?
そこはいただくときの事情にもよりますね。
チョコを渡す女性からすれば、早い話社交辞令といった意味です。
友チョコや逆チョコの意味
近年では女性から男性のみならず、友達同士でプレゼントという意味です。
「友チョコ」や男性側から女性に贈る「逆チョコ」などあらゆる形でバレンタインデーが活性化しています。
時期になると各デパートなどが催事場を組み、期間限定の商品や輸入品などが多く並びます。
この事などからスイーツ好きにとっても珍しいチョコレートを購入できるチャンスがある事も特徴です。
自分チョコの意味

チョコレートを相手にではなく自分を目的とて購入する「自分チョコ」というのも近年の形の1つとなっていて注目されています。
女性の間では、こうして相手にではなく自分へのご褒美としてチョコを買うのも流行っています。
世界のバレンタインの風習
世界の各国での風習としてはチョコを贈るという国は少ないです。
アメリカなどの国では男性、女性関わらず恋人や家族に花やメッセージカードを贈るというケースが多いようです。
ドイツに関しては付き合っているカップルや結婚している夫婦の間だけでやり取りする事となっています。

日本のように片思いの相手に贈るという事は行っていません。
このように日本とは逆のパターンが多い各国です。
なお、変わったところではミャオ族という民族が行う姉妹飯節という恋の祭があります。
このお祭りではミャオ族の女性がきらびやかな民族衣装に身を包みが恋人や結婚相手を探します。
あわせて読みたい記事
このとき、プレゼントとなるもち米を持参して男性にプレゼントします。
韓国のバレンタインデー事情は日本と似ています。
女性から男性に贈るという部分とプレゼントする物がチョコレートである事も共通しています。
結び
バレンタインデーという行事はいつから始まったのか?
この風習は日本では昔からあったものではないですが海外ではどうなんでしょうね。
また、日本でバレンタインを流行らせたのはいったい誰なのか?

なぜチョコなのか、贈る意味は何なのかなどもやはり気になります。
現在では、一般的に行われているイベントのバレンタインデーです。
その起源や由来は興味深い物がありました。
いつから発祥したのか見てみるとその起源は、ローマ帝国時代までさかのぼる必要がありました。
日本で流行らせたのは誰なのかという事にも深く関係しています。
チョコレートの普及の面でもバレンタインの存在は大きな影響を与えています。
昔の日本では非常に高級品であったチョコレートを、何とか一般的なお菓子にしたい。
メーカーとしても売り上げを左右する重要なイベントの1つとなりました。
日本人にとっても定番の行事として大事な物となっています。
中々男性に告白する事ができない女性の方にとっても、良いきっかけとなるイベントですね。
人間関係を円滑にするのにも適しているのがバレンタインデーと言えるのではないでしょうか。

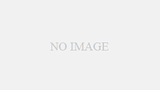

コメント