上巳の節句の意味と由来
上巳の節句は五節句に含まれるもので、日本では3月3日の桃の節句で知られています。
旧暦の3月3日頃に桃の花が咲いたことから、桃の節句という呼び方で定着しました。
上巳は、じょうしやじょうみと呼び、平安時代よりも前にルーツがあるとされます。
これが日本における上巳の節句の始まりで、現在に続く桃の節句の原型でもあるわけです。
当時は貴族階級の一部のみで行われていました。
しかし、やがて武家社会にも浸透して、庶民にも広まり定着することになります。
庶民の暮らしと結びついたのは江戸時代のことで、人形遊びが節句と繋がった結果、行事と化して発展しました。
紙の人形を作り穢れを移して川に流す風習は、ひな祭りにも通じる祭礼の1つです。
ひな祭りのルーツとなったこの風習は、今でも現代において残っているのが特徴です。
昔は5月5日の端午の節句と同じく、男女共に関係なく行われていました。
端午の節句は菖蒲(しょうぶ)の節句とも呼ばれます。
軒にショウブを差すことから尚武と掛けられた結果、男の子のものになったと思われます。
上巳には上句の意味があり、元は旧暦3月上旬の巳の日を指していました。
3月3日に定められたのは、毎年日付が変わらないようにする為で、それが今でも守られ続けています。
上巳の節句は古代中国の上巳節に由来があります。
中国では300年頃に発祥したという記録が残っています。
春をめでたいとお祝いしたり、無病息災を願って行われてきた行事こそが、3月3日の上巳の節句そのものです。
根強く定着している節句でもありますし、割と人々に身近で愛されている節句だと分かります。
上巳は季節の変わり目だけでなく、災いをもたらすと時期と考えられていました。
このため、古代中国においては水辺で穢れ(けがれ)を祓って(はらって)いました。

禊(みそぎ)の儀式が神事と結びつき、人形に穢れを移して川に流す流し雛に変化したことで、日本特有の発展を見せたのが上巳の節句というわけです。
この節句の季節には、日本や中国に加えて台湾や朝鮮などでも、それぞれ催し物の行事が行われます。
上巳の節句の食べ物
上巳の節句では、ひな祭りに縁起物を皆で食べる風習があります。
一般的にはひな祭りの料理という認識が強いので、雛料理と呼ばれることが殆どです。
食べ物はめでたいと掛けた鯛料理や、お祝いの定番ちらし寿司などが代表的です。
はまぐりのお吸い物は、平安時代の遊びの貝合わせに由来するものです。
貝殻が一対になっていることから、仲の良い夫婦を表すとされます。
ひな祭りといえば菱餅も定番ですが、これは上からピンクと白に緑の3色が特徴的です。
色に込められている意味には諸説あります。
一番下の緑は長寿や健康を願うもので、白は清浄、ピンクは魔除けとの説が有力です。
緑色はよもぎでつけられることが多く、増血効果のある実際に健康的な食べ物だといえます。
白餅には菱の実が入れられ、血圧を下げる効果に期待することができます。
ピンク色はクチナシの色で、これには解毒作用があると考えられています。
菱形になったのは心臓を模しているからです。
子供の災厄を取り除こうとする親の気持ちが形になったものだといえるでしょう。
子供は単なるおやつのつもりで口にするひなあられにも、ちゃんとした意味が込められています。
ひなあられは餅に砂糖を絡めたもので、炒って作る上巳の節句定番の和菓子です。
ピンクと白や緑は菱餅に通じますが、もう1つ黄色が加えられている点が注目ポイントです。
上巳の節句の食べ物は更に、白酒やちらし寿司がテーブルに並ぶこともあります。
白酒は桃の花を漬けた桃花酒で、桃が邪気を祓い体力や気力をもたらすとされます。
これも中国から伝えられた薬酒が元です。
江戸時代になるとみりんと米、そして麹を熟成させて作られるようになりました。
現代において子供には甘酒を飲ませるのが一般的です。
ただし、腰が曲がるほどの長寿を願う海老や、見通しを意味するレンコンに、まめに働けるようにと願う豆を加えることが少なくないです。
これまでは料理は家庭で作られてきました。
近年はスーパーやデパートで商品が扱われており、購入して済ませるケースが珍しくないです。
上巳の節句と桃の節句(ひな祭り)の違い
上巳の節句は、上句を表していた上巳節が雛遊びが結びつき、五節句になったものを指します。
桃の節句は上巳の節句の別名です。
雛遊びと融合した結果、女の子の成長を願ったり祝うイメージが強くなっています。
桃の節句は、中国から伝わってきた上巳の節句と言い換えることも可能です。
ひな祭りは女の子の人形遊びが元で、貴族階級の遊びが庶民の雛人形に形を変えたものです。
上巳の節句は桃の節句でもあると考えれば複雑です。
古代中国で発祥して日本に伝わり、独自に発展した考えれば把握しやすいです。
新暦では4月上旬あたりですから、この呼び方が定着したり季節を表す言葉になっているのも頷けます。
桃の花は元々邪気を祓うものとされ、鬼退治の桃太郎でも有名です。
実のところ、3月3日が桃の節句になったのは江戸時代の頃で、上巳節の発祥時期からするととても日が浅いです。
ひな祭りと呼ばれるようになったのは勿論、日本に伝わってきて雛遊びが変化してからです。
雛という言葉は鳥の雛からも想像できるように小さくて可愛いものを意味します。
また、同時に大きなものを小さくする意味合いもあります。
人形を人間に見立て穢れを移し、これを川に流す行事が存在しています。
こうして、貴族の間で遊ばれてきた人形遊びと融合しました。
流し雛と呼ばれた行事では徐々に人形が豪華になり、何時しか川に流すものから飾る形へと変化します。
それが現在のひな祭りに通じるもので、由来となった上巳節との大きな違いです。
しかし、災いの身代わりになってもらうという意味は今も残っています。
このため、嫁入り道具の1つとして嫁ぎ先に持ち込む家財でもあります。
ひな祭りは日本の文化で、元となった節句とは元々違っていたという見方もできます。
いずれにしても、現代ではあまり違いについては深く考えられていません。
春の季節にお祝いをするイベントのひとつと捉えられます。
ルーツや意味について改めて考えてみると、親から子供に対する思いの深さや、昔の人も幸せを願った気持ちが想像できるはずです。
雛人形の飾る期間と処分の仕方
雛人形は元々穢れを移す人形で、この人形は川に流され役目を終えていました。
この風習が飾るものへと変わっています。
では、いつまで飾るかというと3月の中旬には片付け終わっているのがベストです。
つまり、啓蟄の日(けいちつのひ)がおすすめとなります。
現代では嫁入り道具の1つです。
処分せずに保管しておいたり、飾るケースも少なくないでしょう。
しかし、現代的な住宅では保管するにしても場所を取りますし、飾らないという人もいます。
処分が必要になった時は、後悔しないように注意して手放すことが大事です。
雛人形の処分方法には、他人に譲ったり供養してもらうやり方があります。
また、譲渡方法も希望者に直接譲るだけでないです。
買い取りサービスを利用したりオークションを活用するなど、実に様々な譲り方があります。
ただ、後になって買い戻したりするのは難しいですから、本当に手放しても良いか考えてから決めましょうね。
直接譲る場合は相手に雛人形を見てもらい、それから話し合いで決めるのが賢明です。
無料で譲るのか販売という形を採るかは自由です。
しかし、トラブルに発展しないように決めておくことをおすすめします。
優柔不断な対応だと、譲渡を希望する側が困ってしまいます。
どのような形で譲りたいのか譲り方を明確にする必要があります。
雛人形が高級で少しでもお金に変えたい場合は、買い取ってくれる業者やオークションが狙い目です。
業者は持ち込みや出張買い取りに対応していますから、査定を受けてその場で売買が成約できます。
オークションの方は、不特定多数に対して売却を持ち掛けることが可能で、高値に期待できるメリットがあります。
なお、お雛様はもちろんのことです。
そして、お内裏様や三人官女、五人囃子など各人形と持ち物などの細かいパーツにも損傷や紛失がないかも確かめておくのが賢明ですね。
売却後に状態が説明と違うと指摘されると、トラブルに発展して厄介になるので要注意です。
実際に1つずつ清めるとなると大変です。
人形の供養を引き受けてくれる神社やお寺に相談するのが現実的です。
費用が発生するケースもあります。
後腐れなくスッキリと手放せるので、前向きにおすすめできる処分方法です。
手放す人が少なくない現代において、引き取り手が見つかりにくいのも事実です。
こういった供養を提供する施設に任せられると安心です。
上巳の節句の意味|まとめ
上巳は、じょうしと読みます。
これは、五節供(ごせっく)の一つにあたる桃の節句のことです。
ではこの上巳の節句とは、ひな祭りと違う意味のものなんでしょうか?
実は、女の子を祝うひな祭りの正式な呼び名のことなんです。
上巳の節句は、古代中国で生まれ、日本に伝わり桃の節句として定着しています。
宮中行事になった上巳の節句は、民俗行事の流し雛と合わさり現在の雛人形に至ります。
上巳の節句、桃の節句で振る舞われる食べ物は、皆子供の健康を願うものです。
はまぐりや菱餅にひなあられとちらし寿司など、どれもひな祭りにはなくてはならない定番でしょう。
これは桃の花から作られたものではなく、甘酒に置き換えられるようになっています。





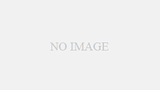


コメント