三人官女(さんにんかんじょ)の並び方
三人官女(さんにんかんじょ)の並び方にはいくつかのパターンがあります。
そのため、飾り方も人それぞれになることがあります。
両サイドの官女が立っていて真ん中の官女が座るケースや両サイドの官女が座っていて真ん中の官女が立つケース。

また、全員立っているケースなどがあります。
なので、雛人形によっては立っているか座っているか、それぞれで異なるケースが多いです。
ただ1体の官女と2体の官女というように分けることができます。
ペアになる官女を両サイド、残った官女を真ん中に置く形になります。
では、両サイドの違いにはどのようなものがあるのかです。

しかし、この場合はそれぞれの女性の足元に注目します。
それぞれの官女は外側の足が多少前へ出ていることが多いです。
これを見て外側の足が前へ出るように配置すれば良いことになります。
雛人形を飾る場所を正面に見た場合、右足が出ているものは向かって左側に、左足が出ているものは向かって右側に並べるような形にすれば大丈夫です。
あとは、真ん中に座っている官女を配置すれば、三人官女が勢ぞろいすることになります。
一方で、3人とも座っている場合、立っている場合もあります。
座っている場合、両サイドの官女を気持ちだけ真ん中に向かせて並べます。
3人とも立っている場合にはまずペアを見つけます。
そして、仲間外れになった官女を真ん中に置くような形で問題ありません。

1体の官女だけ他の2体の官女と異なる理由は、真ん中に配置すべき官女は三人官女の中でも格が上だからです。
例えば、既婚者や年長者が真ん中に配置されることになり、それだけ他とは異なります。
ポーズが1体だけ違うものを見つければそれを真ん中に配置します。
これで、雛人形のことをちゃんと理解して置いている人だと思われるのでそこだけは間違えないようにしたいところです。
バリエーションの違いは購入した雛人形によって違うことは明らかです。

ですが、1体だけ異なるという部分はどれも同じです。
また、ポーズや顔などを見るとここでも仲間外れになるものはすぐにわかるので、そこだけは見ておきたいところです。
特に三人官女はどれも同じような印象を与えます。
よく観察するとちょっとした違いがあります。
それで区別をしてから並べることが大切なんです。
それだけでも覚えておくことで人前で恥をかいたり、子供に雛人形の意味を教える場合などに安心できます。
三人官女(さんにんかんじょ)の役割や見分け方
三人官女(さんにんかんじょ)の役割や見分け方の前に、そもそも雛人形とはどういうものか?
何を表現しているのかというのを知る必要があります。
よく観察してみると三人官女の持ち物で飲み物を注いだり祝儀の置物を運んだりする役割を担っていることがわかります。

実は雛人形は結婚式を示していて、お内裏様(おだいりさま)とお雛様(おひなさま)は新郎と新婦です。
その結婚式を手伝う立場にあるのが三人官女であるため、それぞれにはちゃんとした役割があります。
結婚式を表現するために食べ物を運んだり、飲み物を注いだりするようなことを行います。
市販されている雛人形の中にはこれらの小道具がいったん外されているケースがあります。
これらの持ち物に関しては後述しますが、それぞれの三人官女にはちゃんとした役割があります。
そのため適当に並べてはならないということがわかります。
もし雛人形を自作する場合には、小道具込みで作っておくなどの対策を立てておけば間違う心配はありません。

ここで気になるのが3体とも座っている場合です。
この場合にはどれがどの官女なのか、見分けがつきませんね。
ここでの見分け方に三人官女の顔のメイクがあります。
このようなメイクをする理由はこの中での年長者、もしくは既婚者であることを証明するためです。
既婚者は必ずこのようなメイクを行い、既婚者がいなければ年長者がお歯黒や眉を落とすようなメイクをします。
三人官女の顔を細かく見ると両サイドの眉は細いのに対し、真ん中の官女は眉がありません。

もしくはかなり短くしているケースがあります。
また眉は見えるもののかなり薄くしているものもあります。
どのような形にしているかは雛人形によって大きく異なる部分です。
口元を見ると、両サイドの官女は歯を見せているケースやそうでないケースなど様々です。
しかし、真ん中にいる官女は歯を黒くしているのがわかり、明らかに違いが見られます。
でも、それは実際の雛人形を示したものとは言えません。
実際は、ポーカーフェイスが多く、顔の表情を変えません。
この理由も後述しますが、これらの細かな描写がそれぞれの官女の見分け方につながっていきます。
細かな部分ですが、それが違いでもあるというわけです。
三人官女(さんにんかんじょ)の持ち物や衣装の違い
雛人形に登場する三人官女の持ち物には提子(ひさげ)や銚子(ちょうし)があります。
これを持たされている理由は三人官女が結婚式で振舞われる白酒を注いでいくためです。
足を見ながら並べる場所をチェックできます。

実は持たされている持ち物から並べる順番を推察することも大いに可能です。
基本的に飲み物は提子に入っています。
それを直接容器に注ぐのではなく、まずは銚子に注ぎます。
それから容器に注ぐことから、左側の官女が提子を持ちます。
そして、右側が銚子という順番になります。

では、真ん中にいる官女は容器ということになります。
しかし、直接容器を持っているケースは少ないです。
これをお内裏様やお雛様のところまで運んで、飲み物を飲んでもらいます。
雛祭りの歌にはその情景が描写されています。
次に三人官女の衣装の違いについてですが、実は決定的な違いというものはありません。

なので、必ず真ん中の女性だけ衣装が違うなどのものはないと見て良さそうです。
違いがあるとすればお歯黒をしているかどうかだけです。
3体とも着ている衣装が同じというのが実情です。
特に違いをつける必要がないということです。
市販されている雛人形を見てもどれも同じような衣装となっています。
昭和の雛人形だと真ん中に座る官女だけ色合いの違うものを着せているケースもあります。
ですが、これは少数派です。

現在では3体とも同じのものがほとんどです。
なお、3体とも服の色が違うケースもあります。
この場合には真ん中の官女はこの色でなければならないということはありません。
持ち物には決定的な違いがある一方で衣装にはそうしたものがありません。
結局のところ、役割がそれぞれで異なり、それぞれの仕事を全うしていれば特に問題はないということです。
五人囃子などは明らかに服が異なります。
五人囃子の場合はやるべき仕事、役割が違うからです。
元々の仕事が同じ三人官女の場合には服装が同じであっても不思議ではないです。
なので、別の部分で見分けることになります。
三人官女(さんにんかんじょ)とお雛様との関係
三人官女はお雛様(おひなさま)の身の回りのお世話をする人たちです。
一見するとお雛様の家来のようなイメージです。
しかし、実際のところ、それ以上の関係というのが真実です。

お雛様があれをしろ、これをしろと命令して好き勝手に色々とやらせるような関係性ではないです。
命令が出る前に先回りして身の回りをするようなイメージです。
なので、よほど立派な人でないと成立しないのが三人官女です。
かなりのエキスパートと思われる3人の女性という見方が一番しっくりきます。
仕事が行えて観察力もいいだけでなく、それだけの教養もあります。
なので、お雛様が小さい時から官女は教育を施していきます。
この官女たちは一生涯お世話を行っていくことから、結婚をするとお雛様と一緒に官女もついてくるようなイメージです。
現代に置き換えれば、ずっと世話を見てくれた家政婦が結婚と同時に家まで押しかけるような感じなので、旦那さんからすれば大変です。

官女が非常に重要な意味合いを持つのは、基本的に姫とされる人物は甘やかして育てられるような環境にいやすいです。
最初から両親にきつく育てるよう求められる場合には容赦なく育てられます。
なので、立場が弱いと顔色を見ながら育てられることになります。
すると姫はその姿をすぐに察知するため、官女を困らせるようなことをします。
1人の女性として厳しくも優しく育てられてきた人と自らの立場を利用して自由に生きてきた人ではその資質に大きな違いがあることは明らかです。
雛人形において三人官女はお内裏様などの下の段にいることがほとんどです。
それだけ大事なポジションであり、一生涯お世話をする存在です。

礼儀作法だけでなく、楽器の演奏なども華麗にこなします。何でも出来てしまう人でなければ官女にはなれません。
そのうちのエキスパートが三人官女だと思うとそのすごさには頭が下がり、雛人形を見る目が変わるはずです。
同じような印象かもしれませんが、実はきっても切れない間柄であり、よき理解者、教育者でもあります。
そのため雛人形を見ると、三人官女は3体とも顔の表情を変えないものが多いです。
これもまた喜怒哀楽を出さないことが大人の女性としてのステータスだったことと関係しています。
だからこそ、白粉によって顔の表情が出ないようにしており、同じような雰囲気になります。
官女はそれだけ位の高い存在であり、女性から見れば憧れです。
三人官女の並び方|まとめ
三人官女は雛人形を飾るときの二段目に並ぶ大切な人形です。
ここまではよく見かけるのであなたも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
それでは、三人官女の並びや役割、見分け方についてはどうでしょうか。
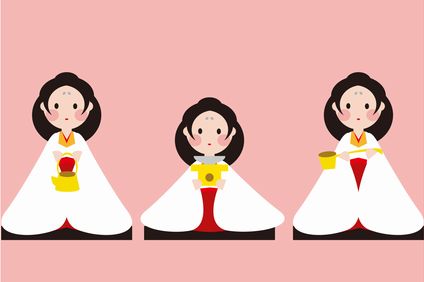
また、それぞれの持ち物や衣装の違いとなれば子供時代の記憶もだいぶ薄れてきていませんか?
三人官女はお雛様と似たようなメイクをしていて分かりにくい、見分け方や並びが分からないという人も多いかと思います。
役割も当然のことながら違い、それぞれの官女にはこなすべき仕事があるというのが分かります。
一方で衣装に関してはどれも同じです。
だからこそ、分かりにくいと感じる理由と言えます。
お雛様との関係も一生涯にわたって続くということを知る人はそこまで多くありません。
なぜ雛人形には三人官女が必要なのか、これまでは謎だったという人もいるのではないでしょうか。
実は一生涯お雛様についていき、お嫁に行く場合も一緒についていく存在であると分かれば見方も変わるはずです。

お雛様と同じようなメイクをしているのも地位の高い女性だからこそです。
三人官女のそれぞれの違いや存在意義、見分け方を知ることでより細かく知ることが出来ます。
なお、雛人形を娘や姪に買ってあげたりお祝いをあげる人、家族で並べる人、自作の雛人形を作りたい人などもいるかと思います。
一般常識を持たせたい場合にもこれらのことは知っておきたいですね。






















コメント