七夕の織姫と彦星の関係
織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)の関係は夫婦です。

そもそも織姫と彦星は恋人ではなく、夫婦が正しい関係です。
星座では彦星こと牽牛(けんぎゅう)は牽牛星と呼ばれており、わし座の主星であるアルタイルを指しています。

一方で、織姫こと織女(しょくじょ)もまた織女星と呼ばれています。
こちらは琴座(ことざ)のベガです。
まさしく天の川を挟んだ位置で輝いている星のことです。
七夕の物語自体は中国から伝わったとされています。
引用:「七夕の星」を探しましょう〜夏の大三角と織姫・彦星(べガ&アルタイル)
その昔、天の川のほとりで「織女」という娘が毎日機を織り続けていました。
彼女は天帝の娘だったものの、遊びもしなければ化粧もしない娘でもあったのです。
牽牛はその申し出を快く引き受け、天帝をきっかけに見合いをした2人は晴れて夫婦になるのでした。
ところが、ここで思わぬ誤算が生まれます。
織姫と彦星は、あまりにもお互いが好きだったため、仕事を怠けるようになりました。
何と結婚で知り合った2人はそれからというもの互いに相手に夢中になります。

その結果、織姫と彦星は全く働かなくなったのです。
いつまで経っても働かない夫婦にしびれを切らした天帝はついに激怒します。
そして、織姫と彦星を引き離しました。
そのうえで天の川の両岸でそれぞれの仕事に励むように命じます。
それから2人は天の川の両岸で以前のように働くようになります。
ただし、もしも七夕の夜に雨が降れば水かさが増してしまい、会う事が出来ないと言われています。

そのため人々は晴天と願い事を祈るために笹の葉を飾り、星空を見上げるようになったそうです。
そもそも織女の父親である天帝が物語を進行しているわけです。
天帝は古代中国の殷(いん)時代からその概念が生まれており、確立したのは周からです。
周において天空の神として信仰されていた「天」、そして殷(いん)で崇められていた卜占(ぼくせん)をつかさどる神である「帝」が習合した結果だと考えられています。
道教では仙人や天神などをまとめる主神であり森羅万象(しんらばんしょう)を司っている存在です。
七夕の物語における天帝はこの道教のほうです。

実際に七夕の物語は天帝が登場する御伽噺(おとぎばなし)として引用されてもいます。
それらを含めて幅広い年代に伝えるのは難しいかもしれません。
けれども、1つ1つの意味を分かりやすく噛み砕き、例として他作品などを引用しながら説明すれば理解してくれる可能性はあります。
その分、資料を揃えたりなどの作業に時間はかかるものの、理解してもらうためのコストと考えれば当然ですね。
七夕の物語を子供にもわかりやすくお話する方法
七夕の織姫と彦星の物語は『ロマンチックな恋の話』というよりも、『怠け者を戒める教訓』となるお話だと言えます。
しかし、子供に怠け者を戒める教訓と説明しても、それが伝わらないことがほとんどですよね。


なので、七夕の物語を子供になじみのあるものに譬え(たとえ)て説明してあげるのがおすすめです。
それには次の2つの方法がおすすめです。
2.別の作品の登場人物に置き換えて説明してあげる
七夕の物語を子供の身の回りの出来事や人間に置きかえて説明してあげる

七夕の物語を直接子供に話すよりも次のような言い換えで説明すると、伝わりやすいです。
・ゲームが楽しくて時間を忘れてしまい、なかなかお風呂に入ろうとしないからお母さんに叱られた
七夕の物語は、あえて子供に問いかけて反応を伺いながら話していく方法がおすすめです。

要するに、子供の身の回りの出来事や人間に置きかえて説明してあげることです。
こうした関連付け的な言い方をする場合は子供に問いかけてみましょう。
反応を伺いながら話していけば、伝わっているかどうかが掴みやすいのでおすすめです。
七夕の物語を子供に別の作品の登場人物に置き換えて説明してあげる
七夕の物語を別の作品の登場人物に置き換えて説明する方法もおすすめです。
例えば子供が好きな作品の代表格であるアンパンマンやドラえもんなどに譬えてみます。

・しずかちゃんがのび太と遊ぶ事に夢中になって家の手伝いをしなくなった。
七夕の物語を子供にこのような伝え方もできますよね。
別作品の登場人物たちにマイナスなイメージを抱かせるのは正直に言えば悪いものかもしれません。

でも子供ってアニメや絵本が好きなのでその作品の登場人物たちに置き換えれば分かりやすいはずです。
また七夕の物語をわかりやすくお話する方法として、アニメや絵本を用いる方法が挙げらます。
絵本やアニメは、そもそも子供にも分かりやすいようにデザインされています。
あえてそうしたストーリーから入らせて、大まかなあらすじを覚えるようになったら正確な物語を教える選択もあります。
正確なストーリーを覚えてしまうリスクもある

先述したアンパンマンやドラえもんなどのように別作品には時節ネタがあります。
そのなかには七夕もあるので、それを引き出して好奇心を注いでから話し始める方法も悪くないです。
この方法は物語の要約だけを伝える時にその効果を発揮します。
このように間違ってはいないけれど、正確でもないストーリーになってしまうリスクが高いです。
しかし長々と説明しても途中で飽きてしまう可能性も否定できないため、要約という選択肢も方法として数えられます。
織姫と彦星のおとぎ話のあらすじ
・それに起こった織姫の父親(天帝)が二人を別々の場所に引き離す
・1年に1度、7月7日の夜にだけ会うことが許される
その昔、天の川のほとりで「織女(しょくじょ)」という娘が毎日機を織り続けていました。
※「機を織り続けて」という表現がわかりにくいので、現代のわかりやすい言葉に直して説明してください。
年頃の娘にも関わらず、毎日働くばかりの織女。
その姿を見て不憫に思った父親は同じく天の川に住む牛飼いの青年、牽牛に「娘と結婚してほしい」と頼みます。
牽牛はその申し出を快く引き受け、天帝をきっかけに見合いをした2人は晴れて夫婦になるのでした。
ところが、ここで思わぬ誤算が生まれます!
何と結婚で知り合った2人はそれからというもの互いに相手に夢中になります。
そして、全く働かなくなったのです。

そして、織姫と彦星を引き離したうえで天の川の両岸でそれぞれの仕事に励むように命じます。
そのうえで「1年に一度、すなわち7月7日の夜だけ会う事を許す」と付け足すのでした。
それから2人は天の川の両岸で以前のように働くようになりました。
そのため人々は晴天と願い事を祈るために笹の葉を飾り、星空を見上げるようになったそうです。
以上が本来の織姫と彦星の物語です。
七夕の由来とは?
七夕の由来は諸説あるものの、現在有力視されているのは次の3つの説です。
2.乞巧奠(きこうでん)という儀式が由来になっている説
3.棚機津女(たなばたつめ)という習わしが由来だという説
②③の説は儀式や祭礼が深く関わってきます。

中国から伝わったと言われている織姫と彦星の伝承を語るうえで、乞巧奠(きこうでん)という儀式が欠かせないです。
乞巧奠とは織姫と彦星の伝承が転じて、女性の手芸や裁縫の腕前が上がるように祈られた行事とされています。
そもそもの話、彦星は牛飼いの青年として登場しています。
牛は生活を支える動物であるとともに、川の神様に捧げれていた動物です。
実際に牽牛とは牽かれる牛、すなわち犠牲になる牛を意味しています。
そうなると織姫もまた当然、儀礼的なシンボルを抱えています。
それが先述した乞巧奠ですが、もう1つが日本古来の習わしだった棚機津女(たなばたつめ)です。
棚機津女とは7月6日に地上に降りてくる水の神様のための布をつくるため、水辺の小屋にこもる女性を指しています。
棚機津女が織った布は神様のための布です。

この水の神様が天に帰る7月7日にお供えして禊(みそぎ)をすれば災厄をはらってくれると信じられていたのです。
また雨不足にならないために、雨乞いとしても行われていたと言われています。
いずれにしても、この3つの説は深く関係しています。
「これら3つの説が融合した結果が七夕ではないか」と囁かれているほどです。
この七夕ですが、7月7日というのは旧暦つまり太陰太陽暦からきています。
そのため、7月7日は『伝統的七夕』と呼ばれています。
今は新暦を使っているので、その年ごとに日が変わります。
2021年だと七夕は8月14日ということになります。
七夕の織姫と彦星の関係|まとめ
織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)の関係は夫婦です。
しかし、あまりにもお互いが好きだったせいで、仕事を怠けるようになった事が引き離された理由です。
そこから七夕に関する儀礼が始まり、江戸時代に庶民に定着します。

現在では子供のための物語として有名です。
そのストーリーを分かりやすく伝えるにはコツが必要です。
あるいは好きな作品の登場人物に置き換えて伝えれば分かりやすいです。
いざとなれば、単純に七夕の物語のアニメや絵本を用いる事も理解してもらうための手段として推奨できます。


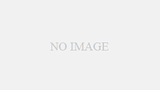
コメント