お食い初めのやり方
中国や韓国を含め、日本では赤ちゃんが生まれて100日目にお祝いをする風習があります。
これをお食い初めや百日祝いとも言い、赤ちゃんが初めてお箸を使う記念日となります。
基本的なやり方としては料理を作り食器も用意して祝い箸を使い食事をさせる方法が基本です。

まずはお食い初めを行う日にちを決めるのが先決で、乳歯が生えるころが目安です。
百日祝いの呼び方もあるくらいです。
やはり生後100日目あたりに行われるケースが多いです。
100日というのはあくまでも目安なので厳密に100日目である必要はないです。
そもそも、乳歯が生え始めるタイミングには個人差があります。
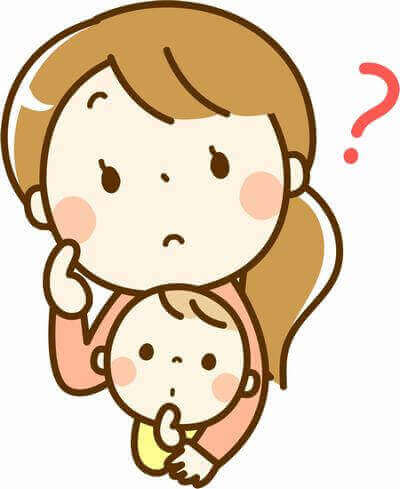
このため、少しくらい日にちが後ろにずれても問題はないといえます。
一般的にはお食い初めの日にちを決めるのに生後100日~120日頃を設定することが少なくないです。
また、お食い初めには食べる順番があって、ご飯を中心にお吸い物やお魚を口元に運びます。
具体的には、ご飯を口元に運んだら次はお吸い物です。
そしてまたご飯と今度はお魚、最後にご飯とお吸い物の順となります。
このパターンを1セットとして、合計3回繰り返すことで儀式の完成になります。
お食い初めで支度するもの
後は歯固めの石に箸先を軽く触れて、赤ちゃんの歯茎に軽く当ててあげれば完了です。
料理を囲んで家族写真を撮影するのもあり、食事は大人たちが美味しくいただいても良いです。
改めて支度するものを確認すると献立には鯛や赤飯にお吸い物と煮物や香の物の5つが献立となります。

食器は漆塗りや素焼きのものが理想的です。
男の子は全て朱塗り、女の子は外側が黒塗りで内側が朱塗りの器を用意します。
祝い箸は柳から作られているのが特徴で、両端が細くなっているものです。
歯固めの石はお宮参りの際に神社で受け取れます。
または、神社の境内から石をお借りすることもできます。

あるいは河川で拾う手もあります。
そのままだと衛生的に懸念されますから、良く洗ってから使うのが無難でしょう。
近年は通販でも取り扱われていますのでネットで購入するのもありですね。
このように、支度するものは沢山あります。
赤ちゃんの健康的な歯を願ったり成長をお祝いする機会となります。
食べさせは原則的に年長者が担うのが習わしです。
そこで、祖父母が身近にいる場合は長寿にあやかってお任せしましょう。

男の子なら男性、女の子であれば女性の年長者が養い親として食べさせていきます。
勿論、食べさせるといっても真似です。
膝に乗せて順番に1つずつ食べさせ、最後に歯固めの儀式をすることが赤ちゃんの幸せに繋がります。
お食い初めの料理の用意は義母?
お食い初めの料理は、用意を誰がするかが悩みのポイントになりがちです。
男親の母、つまり女親にとっての義母が料理を用意するケースが珍しくないです。
ただ誰がするかは明確に定められていないので、実母が作っても構わないといえます。

お食い初めの料理を一緒に協力し合って作るのもありですね。
そこは、義母との関係性に合わせて担当者を決めるのが良いでしょう。
料理に自信がなくて義母に任せたい場合は、お願いして料理を作ってもらうことになります。
頼み方は色々ありますが、例えば食材を用意するので作り方を教えて欲しいお願いしてみましょう。

このような方法だと相手も期待に応えたくなるはずです。
たとえば、お金を出すという頼み方ではあまりにも他人行儀ですよね。
ただし、全てを丸投げして任せるのも距離感を感じさせます。
ところが、材料を用意して作り方の指南を受ける形であれば、お互いにとって抵抗感を生み出さずに済みます。
義母が料理を作りたくて申し出た場合は、その言葉に甘えるのも1つの方法でしょう。
当然ながら食材費は支払い負担して、それとは別にお礼をすることも忘れてはいけないポイントです。 誰かが断りもなく料理を作ってしまうと他の人達が困ってしまいます。
誰かが断りもなく料理を作ってしまうと他の人達が困ってしまいます。
儀式の実施を決めたら早い段階でお食い初めの料理担当者を決定しておきたいところです。
誰が料理をするか決められない、もしくは自分で作ることができず頼める相手もいない場合もあります。
このようなときは、お食い初めの料理を提供するお店にお願いするのもありです。
いずれにせよ、お食い初めの料理は誰かが作らなければいけないので話し合って決める機会が必要です。
順当に考えれば、料理の経験が豊富でお食い初めの経験もある日頃から料理を作っている年長者が適しているでしょう。

普段から料理を作っているなら義父に任せても構いません。
このどれにも当てはまらないというときは、他の人や購入が候補となります。
子供のことは親がしたい、それもまた間違いではないです。
しかし、義父母を関与させないとなると疎外感を与えてしまいますね。
食べさせ役を年長者が担うことからも料理も身近な年長者に相談してお願いするのが賢明です。
お食い初めの料理の自宅での献立や作り方
お食い初めの料理の献立は、焼き魚を筆頭に赤飯とお吸い物、それから煮物や香の物が並びます。
お食い初めのときの焼き魚はおめでたいを意味する鯛が定番ですね。
このため、可能な限り自宅での献立も鯛を用意したいものです。

貴重な魚で値が張ったり入手性も低いですから無理のない範囲で用意することになります。
お食い初めの赤飯は邪気を祓う魔除けの意味があります。
こちらは、作り方は簡単なので間違いなく用意できるでしょう。
お吸い物も同様に比較的簡単な献立で、赤ちゃんの吸う力を願って作るものです。

煮物の具は自由ですが、紅白色を出す為に人参と大根をベースにしましょう。
そこへ旬の食材を加えて作るのがポイントです。また、香の物は季節の野菜や酢の物が適しています。
内臓を丁寧に取り除いたら流水で良く洗い流し、尾や背ビレと腹ビレに化粧塩をしましょう。
ヒレは熱を加えるとバラけてしまうので念入りに塩をすり込むのが正解です。
厚く塗るようなイメージで、少し塗り過ぎても構わないくらいの気持ちですり込みます。
身は全体的に塩を振っていきます。

塩を振るときは、30cmくらい上の高さから尺塩で振りかけていきます。
勿論、塩を振るのは両面ですが、顔の部分は避けるようにするのがコツです。
竹串を踊り串で刺していきますが、この時は身がS字を描くようにします。
焼くのはオーブンを使い、事前に温めておいて鉄板を敷き、網を乗せてその上で焼きます。
目安は200℃だと大体25分~30分くらいです。
焼き色がついて身に弾力が感じられれば、これで鯛の塩焼きの完成です。

最後は串を優しく抜き取り、お皿に盛りつければ一品の出来上がりとなります。
赤飯の作り方は、もち米を研いだら30分くらい水に浸け置き、ざるに上げて軽く水を切ります。
泡が出てきたら火を止めて、ざるに上げたらもう一度水から茹でます。
この作業を2回繰り返し、3回目に固めに茹でたら次の作業に進みます。
土鍋か炊飯器にもち米とささげの茹で汁を入れて、そこにささげを加えます。
フタをしたら強火で沸騰するまで待ちます。
弱火にして10分ほど炊き、15分くらい蒸らせば出来上がりです。
お吸い物の具は貝が定番です。
しっかりと砂抜きをしておき、軽く茹でた三つ葉や豆腐と一緒に煮ていきます。
昆布で出しを取っておくと旨味が増しますから手間を惜しまずに1つずつ作りましょう。
水に浸けて戻したしいたけや、ごぼうとこんにゃくなども切り揃えます。
このしいたけの戻し汁と水や昆布で出汁を取ります。
そこに酒とみりんを加えてアルコールを飛ばしたら醤油を加えて味を調えます。
香の物は漬物でも構いませんが、旬の野菜を酢の物にするのもありでしょう。
他のお食い初めの料理と比べれば、作り方の難易度は低いです。
自宅でのお食い初めの献立において他の料理に手間を掛けることができます。
お食い初めに使うおすすめの食器と理由
お食い初めに使う食器は、男の子と女の子で色の違いがあります。
男の子は朱色のものを使いますが、これは伝統的な理由があって平安時代にまで遡ります。
当時は色で位が分けられていて、根強い男社会だったこともあります。

そのため、お食い初めの食器は位の高い朱色が男の子。
その下の位を意味する黒色が女の子となりました。
現代だと男女平等の意識が進んでいます。
このように厳密には色分けに従う必要はないです。
もし伝統行事と考えて重んじるのであれば男女で色を分けるのが無難です。

お食い初めの食器の選択は自由です。
ですが、最終的にどの色を選ぶにしても一応伝統や理由を頭に入れておくことは大切です。
お食い初めにおすすめなのは丈夫で質感の良さも併せ持つ伝統的な漆器の食器です。
シンプルながらも格調の高さが感じられますから赤ちゃんにとって特別な儀式に最適です。
これなら選択に迷うことがありません。
一式のセットであれば手元に届き次第直ぐに使うことができます。
漆器は思ったよりも軽く、落下しても割れにくい耐久性があります。
お食い初めで使い終わった後も長く大切にできますね。
 ただし、傷がつくので手洗いを必要とします。その点を除けば長期的に愛用できるでしょう。
ただし、傷がつくので手洗いを必要とします。その点を除けば長期的に愛用できるでしょう。
日常的に使う予定があるなら陶磁器で作られているものもおすすめとなります。
質感が良くて適度な重みも感じられますし慣れると手に馴染むので愛用品に変わります。
落とせば割れるので赤ちゃんにはまだ早いです。
なので、儀式で使ってもう少し大きくなってから本人に愛用してもらえます。
素朴な質感を好むのであれば、ナチュラルな仕上げの竹製や木製も有力な候補です。
これらは軽くて丈夫ですし、熱伝導率が低いです。
熱いものを入れても手に伝わりにくいので火傷の心配が避けられます。
実用ではなく思い出の記念品にするなら上質なものを選び名入れをするのがおすすめです。
このように名入れであればより愛着が湧きます。
子供本人は自分のものだと思ったり親の愛情を感じる切っ掛けになるでしょう。
結び
お食い初めのやり方?
食べさせ役がご飯とお吸い物、ご飯とお魚、ご飯とお吸い物を1セットとして繰り返します。
これを3セット繰り返した後に、歯固めの石で儀式を行えば、お食い初めの完了となります。

料理の用意は義母が担うことが多いですが、必ずしもそうとは決まっていないです。
ただ義母が申し出たり義母に任せたい場合は、お願いして任せることになります。
「食材を用意する代わりに作り方を教えて欲しい」
こういう頼み方をすると、義母も期待に応えたくなるでしょう。
自宅での献立や作り方はメインの焼き魚や赤飯に手間を掛け下ごしらえから丁寧に作るのが理想的です。
特に、焼き魚は塩の振り方1つで仕上がりが大きく左右されます。
そのため、手を抜かずに作りたいところです。
おすすめの食器には伝統的なもの、あるいは耐久性が高く長く使えるものがおすすめです。
また、落としても割れにくい赤ちゃん向けが挙げられます。



コメント